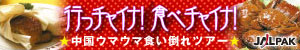富士宮市・第2回B-1グランプリと富士宮やきそばを巡るひる・たびさんぽ(その7)~住宅街に隠れた、これぞジモショクな富士宮やきそばの店「あき」~

前日と合わせて、今回のB-1グランプリに出展している、21種類の料理を一通り食べた後は、開催である富士宮の旨いものを取り揃えたF-1会場から、富士宮の鱒を使った料理3種類をいただくことに。
・富士宮鱒の漬け丼

漬けダレの香りで緩和されていることもあるが、そもそも、川魚特有の匂いはほとんど感じず、箸越しに伝わってくるプリプリの弾力が口に入ると、身の旨みとそれを上回る脂のコクが口いっぱいに広がる。
・イクラ丼

鮭のイクラよりも粒が一回り小さく、皮が少し固めなのが特徴の鱒のイクラ。そんな色鮮やかなイクラがたっぷりと乗ったこの丼、皮の固さゆえに噛んで皮が破れる瞬間には、ちょっとした爆発のような勢いを感じさせ、そこから広がるまろやかな味は、鮭のイクラと比べると濃度を強く感じ、その結果としてご飯とのコントラストを作り出しながらも、しっかり一粒一粒に馴染んでくれる。
もちろん、ズケ丼の上に少しイクラを拝借して食べると親子丼となり、イクラの濃さと身のコクが組み合わさることで、旨々シナジーがピークに達する。
・鱒の塩焼き

久しぶりに、こういった大胆な焼き魚を食べると、皮が焼かれることで生まれる香りに夢中となってしまう。
ハフハフと小骨を口の横に避けつつほおばると、白い身からは凝縮された旨みがあふれ出す。こうなると勢いがついてしまい、ものすごく小さな骨は「よく噛んで食べてしまえ」となる。でも、骨を噛んでいるうちに不思議な旨みがあふれてくるのも、魚一匹を食べるからこその幸せ。

15地区のご当地食と鱒料理を食べてお腹はかなり満たされているものの、富士宮やきそばは別腹。ということで一旦会場を後にして、「ここは特に旨いらしい情報」を元に焼きそば屋さんを巡ることに。

住宅地の中にポツンとたたずむお店「あき」。
住居兼店舗となっているので、店内には大きな鉄板と、それを囲むようにして置かれている6脚のイス、ウェイティング用のイスが2脚。そして、店頭には看板犬が1頭。
地元の方にとって、まるで実家別宅のごとくに、親しまれていることが伺えるように、先のお客さん4人が楽しそうに食事中だったので、ウェイティング用のイスも使って2:2に分かれて食べることに。
で、注文したのは、焼きそばの肉玉としぐれ焼きの肉玉とビールが3杯。下戸の自分は店頭の自販機でコーラを購入して持ち込んだ(「ソフトドリンクはありませんか?」と訪ねたら、お店の方曰く「外の自販機のジュースを持ってきてね」。そんなお店なのだ)。

まず、このお店では鉄板にラードではなく、サラダ油を引いて鉄板の上で伸ばす。
これは理由が2つあって、一つは単純にラードだと重厚感が強すぎるため、もう一つは、このお店、実は出前用をメインとして作られることが多く、冷えても美味しくということになると、ラードよりはサラダ油ということでこちらを使っているとのこと。
ちなみにこのお店、お店の営業開始時間になって最初にやるのは、近所の病院への出前用の焼きそば作り。なので、店頭に暖簾がかかるのは、12:30ぐらいとのこと。

まるで鉄板の上で中華麺やキャベツと会話しているかのように、高温の鉄板と向かい合いながらコテは力強く、それでも温かく動いている。そして、ムダのない一連の動作によって、肉玉ができあがった。

ラードではなくサラダ油を使っているので、全体に口当たりがあっさりとしており、そこにソースが強く主張するかのように絡んでいる。こってり土台から味が始まるラード型とは対照的な味の作り。豚肉やキャベツも大きめに切られているので、具を食べたという満足度も高い。
卵の使い方も、前島では半分まで焼きそばを食べたところで、生卵を落とし入れ混ぜて熱を通すことで、麺に絡めるという作り方だったのだが、こちらは半熟目玉焼きとして提供、黄身をそばと合えてコクを加える。
また、ここのお店のもう一つのポイントが、キャベツの水分の使い方。前島ではキャベツを切った後でザルに入れて水分を飛ばすのだが、ここは逆にキャベツは切ったものをそのまま使う。こうすることで、キャベツの水分が持つ甘みや旨みを、そばがしっかりと吸収してくれるからである。
ラードを使わないと麺のボリューム感に味の濃度が負けてしまうのではと思ったのだが、サラダ油やキャベツを使う、「ウチの店の味」というゴールが明確になっているので、申し分のない作りとなっている。

こちらは、同時進行で作られているしぐれ焼き。ネギがたっぷりと入った色鮮やかなカタマリが裏返されて、たっぷりのダシ粉が振りかけられる。

さっきは、ズルズルとすすって食べていた焼きそばを、生地を通じて具として食べると、その印象は一変。ボリュームの作り方が主食→具となるので、より食べ応えが増すこととなる。
香ばしく焼かれた皮のパリパリとした食感に包まれるのが、蒸し焼きのごとくに瑞々しさを持った麺やキャベツ、そして卵と豚。ここでも、サラダ油+ソースの味設計がいかんなく発揮されており、食べやすさは十二分。
やはり、この2種類を食べてこそ、富士宮やきそばを、あるいは富士宮の鉄板文化を理解できるということ。そしてお店によって作り方に対するポリシーが違い、個々に明確な設計図を持っていることを再確認。こうして、鉄板を空にしてコーラを飲み干して、次のお店へ向かうのであった。